こんにちは、臨床心理士・公認心理師のしあんです。
今回は心理系大学院の試験にもある論述試験の書き方、攻略法について説明していきます。

院試の論述で問われたこと無視して好き放題書いた異端児の筆者が?!

全知人に笑われ尊敬されたエピソード
✓論述って何書けばいいか分かんない
✓感想文になっちゃう
✓正解がないから練習してもこれでいいのか不安
心理系大学院の試験や臨床心理士試験に限らず、論述試験についてのこんな受験生の不安を解消していこうと思います。
今更(?)人にはなかなか聞けない論述の書き方ですが…、本記事を参考にすればきっと形になります。
こんな人におすすめ!
・心理系大学院の受験を考えている人
・臨床心理士試験を受験する人
・論述試験でどう書けばいいか分からない人
・論述対策のために何か指針が欲しい人
論述問題の形式

論述の問題文について少しふれておきますが、以下の形式が多めです。
・~について説明しなさいor論じなさい
・~と対比させながら論じなさい
「~についてあなたの考えを述べなさい」という形式もありますが、基本的には自分が知っている知識を述べていくのがベターな回答です。
×…完全独自の自分の考え
〇…既存の知識や理論に基づいた上での自分の意見
字数制限があれば当然守って「記述欄に収まる範囲で説明しなさい」であればしっかり記述欄に収めましょう。
なお、臨床心理士試験の一次試験(午後)の論述は、必ず指定字数以内で書きましょう!

(字数しか見られていない噂も)
論述の回答の書き方については、①序論、②本論、③結論の3構造でまとめるのがおすすめです!

書き方に悩むならテンプレートを用意すればおk!

筆者も問題は無視したけど3構造にはまとめたなぁ(白目)
①序論
序論では「〇〇とは~である」など、はじめに問題文で出てきた単語の説明や定義を示します。
序論はあくまで自分が持っている知識をアウトプットすればいいので、手短にまとめましょう。
単語の説明や定義をしたら、本論につながるリード文で締めくくると書きやすい&読みやすいかと。
▼例『臨床心理士が従事する4つの専門業務について説明しなさい。』
【序論】
臨床心理士とは、臨床心理学に基づく知識や技術を用いて人の悩みや問題にアプローチする心の専門家である。4つの専門業務として、臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助、臨床調査・研究が挙げられる。
【リード文】
以下に、4つの専門業務についての特徴を述べる。
序論では、みなさんが受験勉強でよくやるだろう参考書のまとめやノート作りが役立ちます!

用語の定義はインプット練習するよね
なので、勉強の際は何も見ないで用語説明を書いてみると論述対策になりますよ。

勉強の際はまず定義を書いて覚える練習をしとこう!
仮に、問題が分からず何を書けばいいか分からない事態に陥ったとしても、自分が分かっていることを書いてみましょう。

筆者も『(問題文)については分からないが(問題文)について分かる範囲で以下に示す』ってリードしたよ
②本論
本論では「具体的には、〇〇とは~である。その特徴としてさらに2点挙げられ…。」など、問題文にある用語や説明上自分が書いた用語についての特徴や利点・欠点、目的などを書き出します。
▼例『臨床心理士が従事する4つの専門業務について説明しなさい。』
【本論】
まず、臨床心理査定とは…である。具体的には~。
臨床心理面接とは…である。
臨床心理的地域援助とは…である。
臨床調査・研究とは…である。
序論で書ききれなかった詳細な説明や、考え・理由を述べる問題であれば「第一に~、第二に…」などど細かく書き出します。
読み手が読みやすいように(書き手が書きやすいように)、1文はなるべく短くするのがおすすめ。

長文は迷走への入り口
本論では、持っている知識をできる限り論理的に表現していく必要があります。
「精神分析について説明しなさい」のようなざっくりとした問題であれば、みなさんが知っている限りの知識を披露すればOK。

「精神分析には大きく3つの特徴がある」など、自分が書けるぞ!って内容を絞って書ければいいかと!
知識があやふやなこと、嘘は書くのは止めておきましょうね。

余計な減点のもと
③結論
「以上のことから、〇〇は~である」「これら3つの根拠から、~と考える」のように、結論では本論で書き出した根拠や説明を踏まえて問題文を復唱したり自身の考えを述べましょう。
▼例文『臨床心理士が従事する4つの専門業務について説明しなさい。』
【結論】
以上のように、臨床心理士には4つの専門業務があり、これらの業務を通してクライエントや地域社会に対し貢献することができる。
結論なのでまとめの言葉でOK。
その論拠になる内容は本論で表現するので、追加で書き出したい知識は本論に含めましょう。
問題文についての課題や問題点があれば結論で述べてみてもいいと思います。

でも「~ではないか?」みたいな疑問の投げかけはNGね。試験だからね、ちゃんとした文章で書こうな
論述の回答づくりで気をつけるべき小ネタ3つ

論述の中身には直接関わってこない小ネタですが非常に大事なことです。
回答以外の些細なことで減点されてはもったいないので、気をつけられるよう頭の片隅にインプットしてみてください。
①大きく、丁寧な字で書くこと
試験官の教授(年配も多い)にまずは読んでもらう必要があります。
どんなに素晴らしい論述でも汚い字はそもそも読んでもらえない可能性が…(特に院試)。

『多くの論述読むんだから汚い字は論外』って教授が言ってた
マークシートと違い、採点は生身の人間が行います。
読みやすい字は受験時に限らず社会人になってからもマナーですので、しっかり心がけましょう。
序論、本論、結論で段落を変えるなどの読みやすさも意識しておきましょう。
②回答を作る前に書きたいことをおおまかにメモする
※いきなり回答を作ってもOKですので、その人のやり方にもよります。
いきなり書き始めると迷走しがちな人は、事前に書きたいことを大まかにメモすると、考えの整理に使えるかと。
ただし、メモしすぎると論述時間が足りなくなる恐れがあるため、単語程度に留めましょう。

書けなきゃ意味からメモは雑に!単語で!
③文体は「~である」調
論述なのに感想文になってしまう人は「~です・ます。」や「~と思います・感じる。」になっているかもしれません!
論述の表現は論文形式が基本です。
・「~である」
・「~と思われる」
・「~と考えられる」
このような表現で書くよう心がけましょう。

(ちょっとカッコよくなるね)
おわりに:序論・本論・結論の構造で書こう!

試験における論述の書き方や書く内容のポイントは、インプットした多くの知識を論理的に表現することです。
その際に①序論、②本論、③結論の3構造を意識すると書きやすく・読みやすくなります。

前菜→メイン→デザートとかイメージしやすいように覚えとこう!
本記事の例で言えば以下のようになります。
▼例『臨床心理士が従事する4つの専門業務について説明しなさい。』
【序論】
臨床心理士とは、臨床心理学に基づく知識や技術を用いて人のこころの悩みにアプローチするこころの専門家である。4つの専門業務として、臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助、臨床調査・研究が挙げられる。
【リード文】
以下に、4つの専門業務についての特徴を述べる。
【本論】
まず、臨床心理査定とは…である。具体的には~。
臨床心理面接とは…である。
臨床心理的地域援助とは…である。
臨床調査・研究とは…である。
【結論】
以上のように、臨床心理士には4つの専門業務があり、これらの業務を通してクライエントや地域社会に対し貢献することができる。
論述の練習方法は、実際に問題を解くもよし、日々の勉強で専門用語の定義をアウトプットするもよし。

書くのがおすすめ
正しく書ける知識を増やし、3構造に倣って論理的に書くよう心がけましょう。
\臨床心理士指定大学院の論述対策/
知識を書き出す練習は是非やっておきましょう!
試験1ヶ月前にやってみるだけでも違いますよ。

「やる」と「やらない」は全然違う。ファイト!

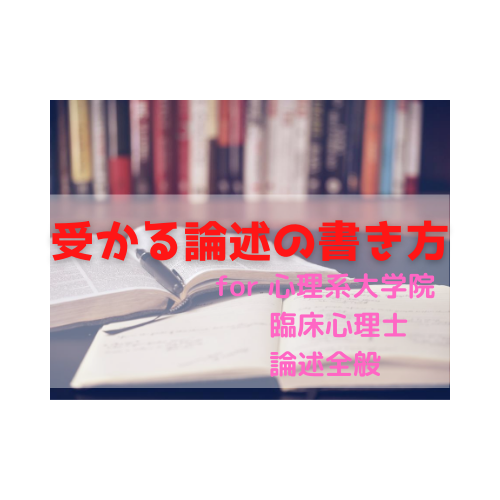


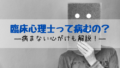
コメント