こんにちは、臨床心理士・公認心理師のしあんです。
心理職をやっていると「いつも暗い話ばっかりきいてしんどくならないの?」とよく聞かれます。
『ミイラ取りがミイラになる』ように、心理士が心を疲弊させてうつ病になったり、資格更新を止めた…などは実際に少なくありません。
今回は、心理士が病むリスクや人が病まないためのポイントについて説明します。
心理士に関心がある人~日常で相談を受けたときに気持ちが引っ張られやすい人まで、潰れないための参考になれば幸いです。
こんな人におすすめ!
・臨床心理士や公認心理師など心理職を目指している人
・現役心理士で病みかけている人
・病みやすく、予防策を少しでも知りたい人
\ うつ病を確認 /
心理士が病みやすい2つのリスク
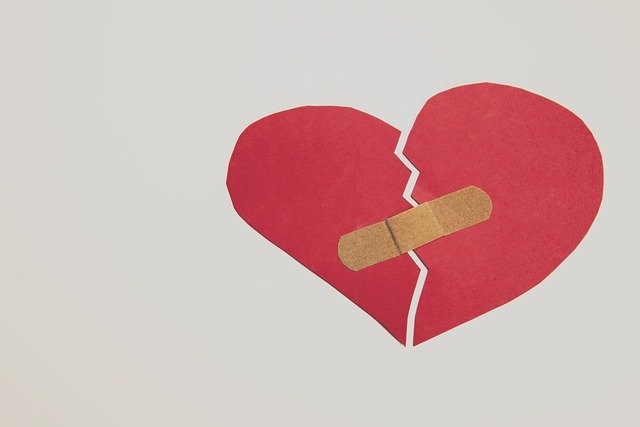
人の悩みや相談をきくことは誰しもが日常でできることですが、それを仕事とした心理士の病みやすいリスクを紹介します。

※筆者の主観です
これらは心理士でなくても、日常で献身的に人の話をきく人にも言えるリスクかと思います。
頭の片隅に改めて置いておけると、病まないようにケアしやすいかもしれません(&関わり方が慎重になれるかと)。
①他者のネガティブな感情を受け止めること
心理士の一般的な業務であるカウンセリングでは、基本的にクライエント(相談者)の相談や悩みを丁寧に聴くことが求められます。
・友人関係のトラブルについて
・心の悩みについて
・精神病の症状について
・死にたい悩みについて など
クライエントの抱える問題は様々でレベルも違いますが、基本的には困り事を聴くのが仕事ですね。

積もり積もればメンタルやられるかもだよね
カウンセリングでは時に「死にたい」という命に関わる相談を受けることもあり、他者の苦悩を受け止めていきます。
たとえば死にたい気持ちを抱えて苦しんでいるクライエントに対し、心理士が聞きたくないから「その話は止めましょう」とは言い難いです。

そんなカウンセラーは嫌だ
また、話の中でクライエントが友人や家族など周りに対して抱いている怒りや暗い感情が、心理士に向けられることもあります。

投影と言います。本来はその友人や家族に向ける感情ですが…。カウンセリングで表現できる分には悪いことではないと思うよ
多くのクライエントのネガティブな相談や悩みに関わり続けることが、うつや落ち込みの引き金になりやすいかもしれません。
②他者の人生に大きく関わり、常に影響を与えうる責任感
私たちが困り事を信頼できる相手に話すとき…。
相手の意見や助言を聞いて行動したり「そういう意見もあるんだ…」と自分の中に落とし込んだりすることが多いですね。

つらいと助けて欲しいもんね
何かに苦悩しているクライエントにとって、心理士の発言・助言は常に影響力をもっています。
クライエントの価値観を変えうる可能性や、クライエントの問題行動を助長させてしまう可能性もあることは、心理士にとってとても大きなプレッシャーで潰れかねないリスクでしょう。

言葉にすると重いね…

ある意味常に加害者になりうる意識はもっておく方がいいぞ
※日常会話でも些細な言葉に傷つくことがあります。日常でも言葉のチョイスには気をつけましょうね
心理士に限らず「人の相談にのるのが好き」というだけでは荷が重いことも案外多いです。
クライエントの中にはリストカットなど自傷行為をして苦しんでいる人も少なくありません。
場合によっては他者の命にも関わりうる責任感もあるため、真面目な心理士は病みやすいのではないかと思います。

話を聴くリスクを知ってると簡単に相談業はできないかと…!
心の健康を保つための6つのポイント
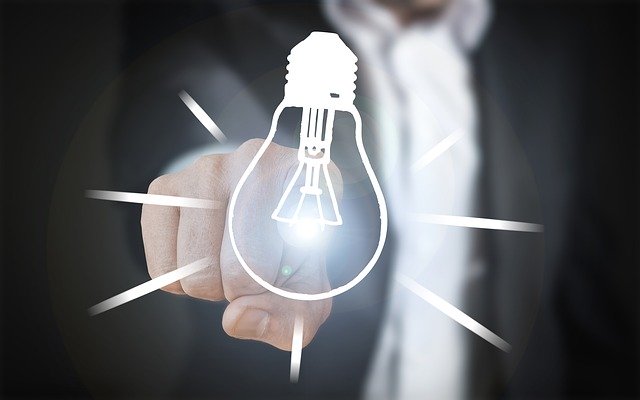
他者のネガティブな話を聴くことがもはや仕事の心理士ですが、我らが潰れないように気をつけているポイントがあります(筆者だけ?)。
①自分が抱えきれないことはきちんと認めて、他者に相談する
②時間などの枠を守る
③話を聴く際に『同調』せず『共感』を意識すること
④境界線をしっかり保つこと
⑤自分のプライベートな感情は特に整理しておくこと
⑥適度な息抜き
人の悩みをよくきく人や病みやすい人も意識できると少しは心の健康が保たれると思います。

自分を大切にするポイントをもっておこう!
①自分が抱えきれないことはきちんと認めて、他者に相談する
カウンセリングは人のネガティブな感情を受け止めることが求められますが、そもそもの疑問があると思います。

どんな話題も自分を殺して聴き続けなきゃいけないの?

待て待て。そう考えて自分が抱えきれない感情を無理に抱えようとすると潰れちゃうぞ
心理士とはいえ人間です。
本当に抱えきれない話題や感情は自分を潰してまで無理する必要はないと思います(抱えられるように自己研鑽はもちろんします)。
共倒れしてしまってはクライエントにも自身にもメリットがありません。
心理士の場合は、クライエントの悩みをよりきちんと受け止められそうな心理士や相談機関を紹介したり(リファー)、自分がネガティブな感情を抱えられるためにもベテラン心理士に話をきいてもらう(スーパービジョン)など、アクションを起こします。

専門家するなら抱えられない話だとしても責任は持とうね
日常で相談を受けるみなさんも、何でもかんでも聞くのではなく、抱えきれない他者のネガティブな感情は無理して抱えなくていいかと。
話を聴いたうえで苦しくなったりするなら、その気持ちはまた人に相談してみてくださいね。
②時間などの枠を守る
何時間も、無限に人のネガティブな話は誰だって聴き続けられないと思います(長時間話を聴けるのがすごいってわけでもありません)。

無限はMURI
心理士はカウンセリングで1回30分や50分、週に1回、同じ部屋でなど相談を聴くにあたっての外枠を設けて大事に守っています。
\ 枠の重要性もチェック /
心に秘めた見えない悩みごとを扱うからこそ目に見える形で枠を用意し守ることが重要で、カウンセラーとクライエントの両者の心の健康を保つ意味もあります。

無限にネガティブな話を聴く側も勿論、話す側もネガティブに火がついて落ち込んでいく可能性があるからそれを阻止する意味もあるよ!
これって日常での相談ごとでも同じことが言えます。
ずーっと暗い話を聴き続けるのではなく、お互いがより暗い方向へ堕ちていかないためにも約束事を決めてみましょう。
・「学校・仕事もあるし土曜の夜だけなら相談にのるよ」と頻度を決めてみる
・「空き教室なら人いないしここで話そう」と話す場を用意してみる など
これだけでも人のネガティブな感情を扱うしんどさはだいぶ減ると思います。
③話を聴く際に『同調』せず『共感』を意識すること
カウンセリングの基本には『共感』がありますが『同調』はNGです。

イメージとしては『共感』は客観的な考えを持ちつつ寄り添うことで、『同調』はクライエントの主観のみで話し合うことかな
聞き役としてあくまで客観的な考えを持ちつつ「それは悲しかったですね」などと共感するのと、「分かるー!めっちゃ悲しい!あいつうざー!」など同調してしまうのは、実際体験してみないと分かりづらいですがかなり感情の揺れ幅が違います。
同調することで心理士(聞き役)の感情まで大きく乱れて冷静に話をききづらくなってしまいます。
困りごとを冷静にきくためにも、話し合っている2人を客観的に眺めるイメージをもってみましょう。

話は丁寧に聴くけど、あくまで相談側ときき手は別な人間だよって感覚をしっかり持とう

重ねすぎると『ミイラ取りがミイラにな』っちゃう
④境界線をしっかり保つこと
話をきいて相手との信頼関係ができてくると、話を聴くための約束事にルーズになってくる人もいますね…。
「可哀そうだからもっと長い時間話をきいてあげよう」
「すっごく気持ち分かるから自分も一緒に〇〇やってあげよう」
良かれと思って行動しても、良いのは自分であって、相手のためになるかは分かりません。

これが本当の余計なお世話
決めた約束の範囲内で話を丁寧に聴くでも十分相手のためになれるはずです。
心理士や献身的な人がうつ病などで潰れないためにも、やはりどこまで力になれてどこからは手を出せない領域なのかをはっきりさせておけるといいと思われます。
⑤自分のプライベートな感情は特に整理しておくこと
心理士(聞き役)自身が問題だらけで心がすさんでいると、クライエントにその感情は投影されてしまいます。

平たく言えば八つ当たりとかね
誰にだって問題や困りごとはあって、それは別におかしなことではありません(心理士・聞き役に不健康な部分があってもそれは仕方のないことかと)。

完璧な人もいないもん
ただ、心理士(聞き役)が自分のことでいっぱいいっぱいだと、そもそも他者の悩みを聴く余裕がありません。
きちんと他者の話を聴けるように、自分自身の悩みや考えを整理したり誰かに相談したり、早めに落ち着かせることをおすすめします。

人様の心のケアの前に自分のをケアも!
⑥適度な息抜き
何事にも言えますが、何でも同じことを延々としていたら息が詰まってしまうので、やはりメリハリが大事です。
・遊びに出かける
・別な仕事をする
・趣味に没頭する
・完全にオフな日を作る など
何でも構いません!相談から距離を置くことも大事!!
他者の話を親身に聴くことと自己犠牲はイコールではありません。
自身の心をあえて癒してあげる時間作りも必要なことですよ。

筆者もよくお喋りしたりカラオケに通うね

人の話は仕事と割り切っているから深い話を聴けるってのもある
筆者の場合とまとめ:献身的との線引きを!

心理士はうつになりやすいかというと、そういう訳ではありません。
ただし、対人援助職はうつなど心が潰れるリスクは十分にある仕事とは言えます。
心理士だって人間なので、問題はあるし病むことももちろんあります。
ですが、気持ちが潰れないように工夫をすれば心理士として働くことは十分可能です。

コツは積極的に自分を甘やかすこと←

つらい経験してもも乗り越えれば病まない強さに変えられるかもね
それでも目の前の他者が「死にたい」と吐露したり、心が痛むつらい状況であったりなどで共感して苦しくなることもあります。
筆者としては、『④境界線をしっかり保つこと』を特に重要視して心の健康予防をしています(他も大切だけど!)。
冷たい言葉に聞こえてしまうかもしれませんが、『自分は自分、他者は他者』という自他の境界線は特に意識する方がいい境界線になると思います。
「とにかく話をきいてあげたい」「他者を助けてあげたい」という思いも素敵ですが、クライエントとの距離が近づきすぎて、揺さぶられて、共倒れになっては…悲しすぎます。

同情に飲まれたらセラピーにならんね

心理士さん基本真面目で献身性高い気がするから、潰れやすさはあるかも
今回紹介した潰れないためのポイントに加えて、精神病の知識や適切な紹介ができるように紹介先の知識もつけ、勉強することも予防の一環です。
相談を受ける人はみな『①自分が抱えきれないことはきちんと認めて、他者に相談する』をモットーにしてもいいかも。

潰れる前に無理せずれっつ相談!

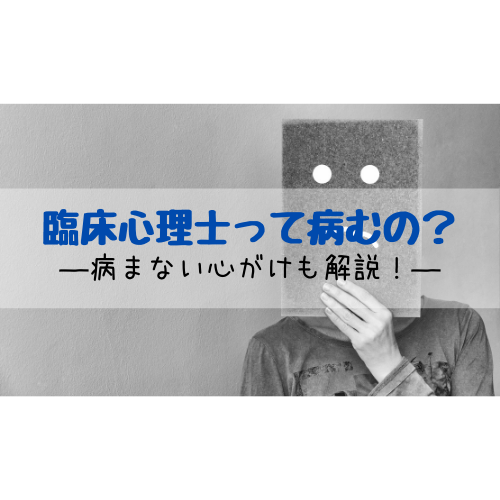

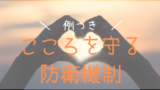
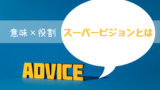

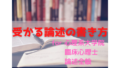

コメント