こんにちは、臨床心理士・公認心理師のしあんです。
心理系大学院を無事に修了したら、いよいよ臨床心理士・公認心理師の資格取得に向けての動きが始まりますね。
修了後、半年ほどの受験期間をどう過ごせばいいか悩む人も多いと思います。
今回は筆者の実際の経験談を踏まえて、資格取得までのおすすめ対策や試験の実際を説明していきます。
なお、公認心理師資格試験の実体験&解説はこちら。
こんな人におすすめ!
・臨床心理士資格試験の具体的な流れを知りたい人
・経験者の生の声を聞きたい人
・受験の不安を減らしたい人
※受験生は必須!
令和7年度の臨床心理士資格試験のスケジュール
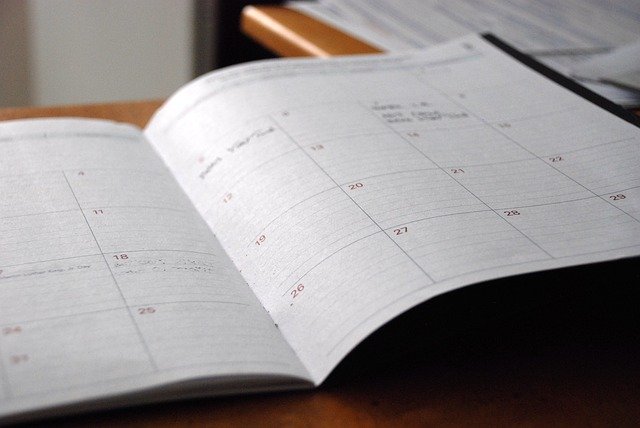
まず、令和7年のスケジュールは下記の通りです。
| 資格審査申請書類請求期間 | ※例年7月~お盆頃 |
| 受験申込受付期間 | 8月31日(日)まで(消印有効) |
| 一次試験(筆記) | 10月11日(土)@東京ビッグサイト |
| 二次試験(口述面接) | 11月22日(土)~24日(月)@東京国際フォーラム |
| 合格発表 | ※例年12月下旬頃 |
詳しくは資格認定協会HPで確認できるので、受験者は必ず目を通しましょう。
試験スケジュールが確定するとその年度の『新・臨床心理士になるために』(誠信書房)が出版されます。
スケジュールだけでなく臨床心理士に関する説明や前年度の過去問の抜粋も載っているので受験者は購入していいと思います。
\ 受験年度分は購入必須!/
筆者の対策の流れ

筆者の場合は大学院修了後から勉強しようという気持ちだけは持っていましたが、実際勉強し始めたのは院卒後の5月頃からだったと思います。
何故かというと4月から常勤で就職し、就職先に慣れたり日々の仕事を覚えたりすることでいっぱいいっぱいだったからです…。

言い訳ベイベー
少し話が逸れますが、大学院修了時点で臨床心理士の資格は当然ないため、修了後は以下のスタイルで過ごしやすいかと思います。
・大学院の相談室に残って勉強に専念する
・2~3日のパート+試験勉強
・フルタイム+試験勉強
後述しますが、仕事の内容や何故パート・就労しないかなどは面接で聞かれました。
現場経験は一次対策も兼ねるため、個人的には何かしら働くことを推奨します。
\ 心理の就活や働き方 /
話を戻しますが、筆者なりに気持ちはあったので3~4月中は参考書や過去問を入手して勉強環境を整えていました。
筆者が使用した2冊はこちら。
\ 参考になった参考書 /
\ 正規の過去問は絶対! /

この2種類あれば十分事足りるかと!
もちろん、心理系大学院の院試で勉強した内容も臨床心理士資格試験に役立つので、過去に使った参考書やノートがあればその見直しも有効です。
筆者の対策スケジュール
就職した年の5月頃から参考書に目を通しつつ、最新の過去問からさかのぼって順番に解き始めました。
個人的意見ですが、参考書を先に一通り読み込もうと思うとかなり時間がかかるのと、ある程度理解している分野の見直しは時間ロスになってしまうため、先に過去問を解くことを推奨
臨床心理士資格試験の内容は過去問と似た内容もいくつか出題されるため、過去5年分くらいをきちんと解くことをおすすめします。
特に、古い過去問を解く際は、DSMや法律など古い情報も多いため除外するように注意。

筆者は5年分くらいは確実に回答できるようにして、順次さらにさかのぼったよ
2、3年分くらいやると少し出題傾向が分かるので、筆者はよく出ていると感じた分野のテキストを読み込んで知識補完していきました。
また、最近では国家資格の公認心理師との差別化を意識しているのか、心理学の知識や歴史、各心理療法に手厚い印象があります。
・フロイトやユング関連の知識
・3大心理療法を中心に、各療法の知識
・ロールシャッハ、PFスタディ、知能検査の手順や解釈
いつの時代もロールシャッハやWAIS・WISCなど心理検査の解釈についてや、法律関連は出題傾向が高いのでしっかり見ときましょう。

検査の種類はむしろ出題がどんどん増えてる印象
なお巷では、『一発合格!臨床心理士対策テキスト&予想問題集(ナツメ社)』の付録の予想問題集が難易度高く、これで6、7割できていれば安心という噂もあったり(真偽は不明)。

実際の試験のボーダーラインは6割くらい!
過去問では満点がとれるくらいには繰り返しやっておくことをおすすめします。

問題の答えを覚えちゃったら、一旦過去問から離れて息抜きしたりテキストで知識の補充をしとこう
筆者の勉強スタイルはこんな感じ。
| 平日 | 仕事後に過去問1~2年分解いて採点(&仕事での勉強) |
| 休日 | ↑正誤の詳細チェック&分からなかった分野をテキストで知識補完 |
仕事で心理検査のテスターをすると、正しい手順や解釈の仕方を実践しながら勉強できるので仕事の勉強も真剣にしましょう!
過去問1巡目は確認の意味も込めて、正答した問題についても調べておくと定着しやすいと思います。

5択の中で知らなかった内容は拾っておこうね
試験対策の流れは、“過去問一通りやったらテキストに戻って怪しい分野のノート作り”をループしました。
勉強ばかりでなく、書類請求や受験受付も忘れずに並行しましょう!(勉強してもコレ忘れたら終了…!)
一次試験(筆記)
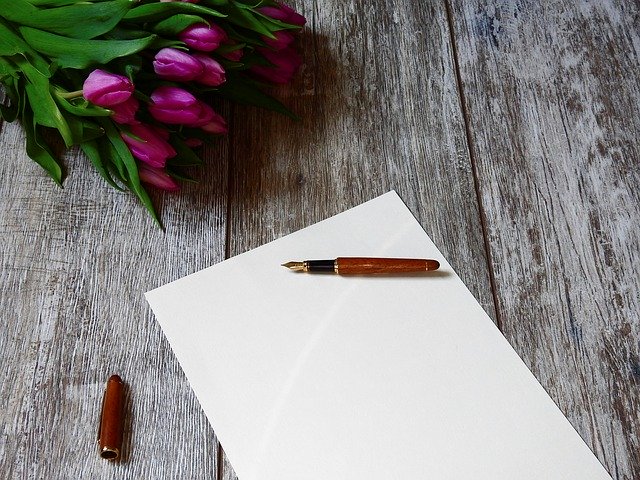
試験は東京ビッグサイトという大きな会場で行うことが多いです。
経験者がよく言うことですが、会場はけっこう冷えるので防寒対策は何かしら用意しておくのが無難。
\ 何でもいいぞい /

筆者は耐えたけどブランケットやカイロ持参の人は多かった
試験前は会場に先入りして勉強している人が多いらしい、です。

筆者はその雰囲気が嫌でギリギリで会場入りしたから知人情報
試験会場には遅くとも30分前には到着しておくと安心かと!
当日の流れは、午前にマークシート、午後に論述。
お昼休憩には近くのコンビニが利用できますが、当日はとんでもなく混むので昼食は買っておく方がベター。

近場だとコンビニくらいしかないような…
筆記試験はとにかく最後までマークする・書くことを心がけましょう(当たり前)。
論述は文字数さえしっかり守れば(中身薄くても)大丈夫です。
論述内容は、どんなこと書いたかは試験後にメモりましょう!二次で聞かれることあります!
個人的には、常勤でも非常勤でもいいので大学院以外の現場で仕事をしている方が、論述内容は書きやすい印象がありました。
その年にもよりますが、自身の経験を踏まえての記述がけっこう多いからです。
筆者の年のテーマは『臨床心理士の専門性と独自性について踏まえ、自身の体験をもとに、クライエントにとって自分が如何に役立ちうるか』を論じる内容でした。

仕事を絡めれば書き進めやすいよ
論述前に構成を考える場合は、細かくメモせず大まかにしておきましょう(時間内に指定文字数で収めることが最重要!)。
二次試験(口述面接)

一次試験の合格者だけが二次試験(口述面接)に進めます。
「一次試験の結果の封筒の厚みで分かる」とか噂もありますが、一次を通過しても封筒は薄いです(笑)

封筒薄くて落ちたかと思った
二次試験の日程は例年2~3日ありますが、曜日も時間も指定されるので基本的に選べません。
一次の合格通知書に二次の案内も書かれているため、原則その日程に従いましょう。
二次試験も東京で行われるため、遠方からの受験者はまた旅費がかかります!泊まるなら宿代もかかるため要準備
遠方からの受験者は楽天トラベルなどで事前にホテルを予約すると、前日入りで安全に面接に臨めたり、面接後に東京で遊べたり…。
\ 一次通過後早めに予約を /

折角なら遊ぼ!!!

楽天ならポイントバックも少しはある=微妙に安く泊まれる
また、大学院の同期(と昨年落ちて今回一次通った先輩)と口述面接の時間帯は被るので、知り合いが一次を通過したかがその日に分かっちゃいます…。

(いない同期がいるとなんか気まずいやつ)
面接官は2、3人で、けっこう距離が離れていたので個人的にはあまり緊張しなかったです。
筆者の場合は和やか&受容的で、他の部屋より早く終わりました(10分程度)。

他所より早く終わっても「落ちた?!」って何でも思うやつ
面接時間は基本15分程度。面接官によってやや時間が短いこともあり。圧迫な雰囲気もあり。でもどれも落ちる前提ではないので落ち着いて!
二次試験の面接内容
聞かれた内容はこんな感じ。※()は回答。2人から質問されました。
・一次の論述はどうだったか(考えさせられた)どんなところが?
・今何の仕事をしているか、雇用?(テスターもしている)どんな検査を取っているか
・どんなケースを持っているか
・臨床心理士を取得してどんな専門家になりたいか、どんな領域で働きたいか
・今まで大学院も含めての臨床経験で身についたことは?
・自分のどんなところがこれからの課題?
・SVは受けているか
・職場にはどんな人がいるか
・職場でどう連携しているか、どんなことに気を付けて連携しているか
面接対策ですが、長々話そうとすると何喋っているか分からなくなって焦りやすいと思うので聞かれたことに手短に答えましょう!
向こうからけっこう質問されます。

必勝のコツ①ボロを出すな
また、現在の仕事内容については聞かれることが多いようです。
非常勤で週1~2日程度の仕事が少ない同級生は修論についてけっこう聞かれたとか(研究重視と思われる?)。
社会人経験者は「何故臨床心理士を目指したか」を突っ込まれやすいようです。
公認心理師ができてからは「2つの資格がある中で、何故臨床心理士を(も)取ろうとするのか」と聞かれることも増えたようなので、自分なりの考えをちゃんと整理しておこう
全体的に受け答えについては、なるべく謙虚になりましょう。
これから心の専門家になる我々の人あたりはばっちり見られていると思います。

必勝のコツ②驕るべからず

この人感じ悪いな…って知り合いは大抵二次で落ち…
ちなみに服装ですが、スーツが圧倒的に多かったのでスーツスタイル(私服ならスーツスタイルに近い恰好)が推奨。
清潔感のある、きちんとした格好で臨みましょうね!

こういうときにジーンズはまじであかん
合格発表とその後

二次試験受験から約1か月後の12月中旬~下旬頃に合否の郵便物が届きます。
それから手続きを済ませると、次年度の4月からは臨床心理士です。
なお、臨床心理士は民間資格で、取得後5年ごとに更新の必要があります。
5年のうちに必要な領域で15ポイント以上取得しなければならないので、取得後も専門性の質を維持・向上させるための研鑽が必要になります。
▼臨床心理士更新のためのポイント取得例
・資格認定協会主催の会へ参加
・各学会に入会・参加
・研修会に参加
・SVを受ける
・資格認定協会が認める著書出版
詳細は臨床心理士資格認定協会をチェック。最近はオンラインの会などもあり。証明書は必ず保管
\ 筆者の初更新 /
更新はまだ先の話ですが、長かった臨床心理士試験の締めくくりに認定証の賞状がもらえるので、なんだか感動しましたね。

頑張った自分への褒めと資格取って少しの喪失感があったなぁ
おわりに:一次は過去問、二次は謙虚に!

大学院を修了したら、あとは資格試験をクリアするだけ。
筆記の内容は本当に過去問で見たことある問題が多いのでとにかく過去問を信用してください。
\ 1冊選ぶなら絶対これ /
勉強は過去問中心に、分からなかった分野をテキストで補完するを繰り返すのがおすすめ。
口述面接は明るくにこにこ、謙虚にで10~15分くらい乗り切れるので、質問されたことに簡単に答えましょう。
臨床心理士になる前も取得後も情報共有は大事です。
経験者の方で経験談の補足があれば是非コメントいただけたらなと思います。
受験生の不安解消にもつながりますし、臨床心理士のつながりが少しでも広がればまた幸いです。

長くなったけど、受験予定のみなさんあと少しがんばれ!

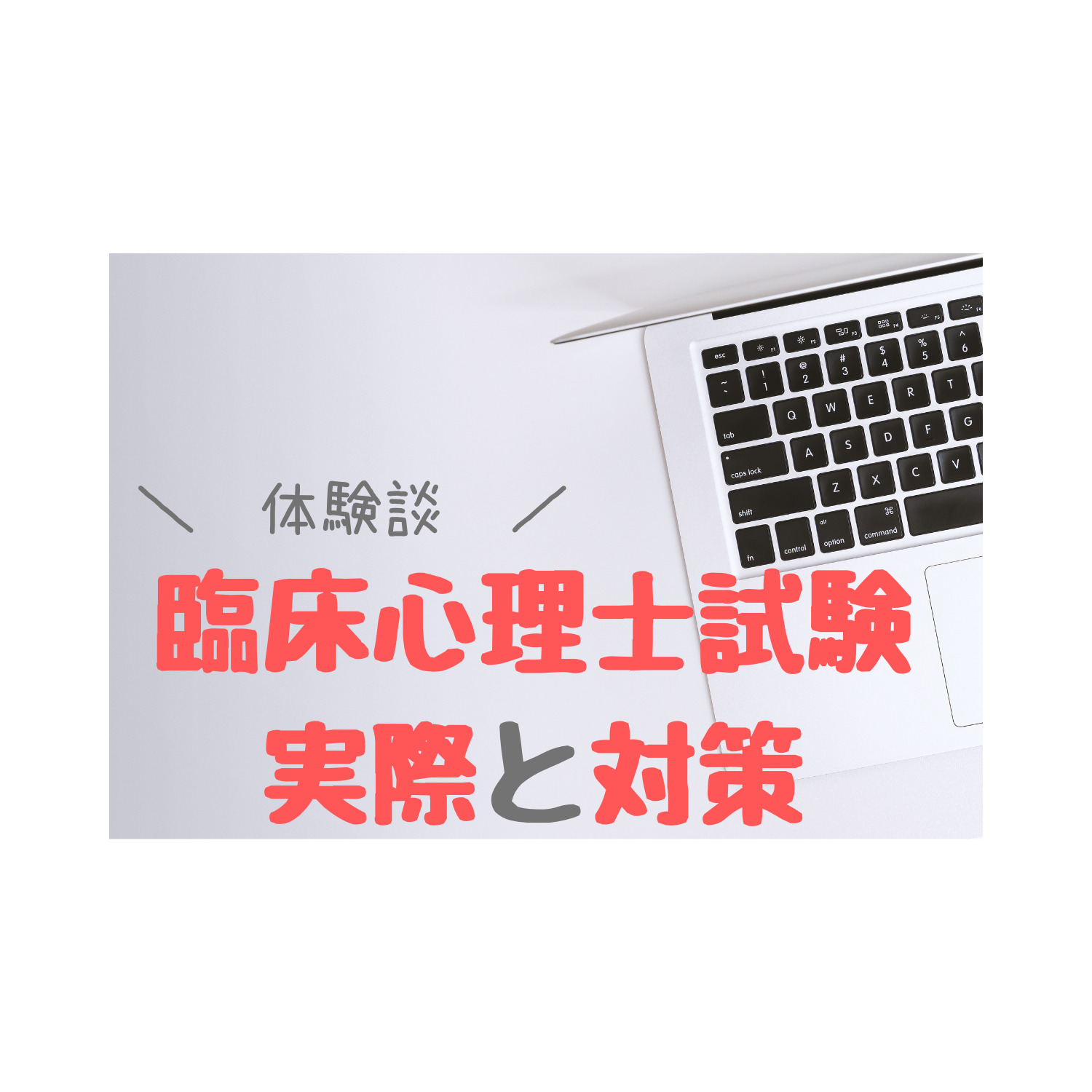
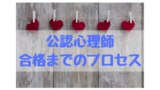






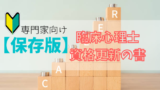
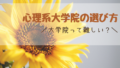

コメント